勉強を進めるために注意すべきこと。
まずは子どもとよく話してみよう
勉強を進める前に、まずは子どもの心境や、本人が感じていることの理解が大切です。
勉強に手を付けられる状態でないお子さんの場合もあります。親御さんが子どもの気持ちに寄り添わず物事を進めてしまうと、今の状況を悪化する可能性があります。
勉強を進めるために大切なことは、話しやすい信頼関係を築いておくことです。
厳しくあたったり、否定的な態度を取ると、お子さんと心の距離が生まれてしまいます。できるだけ共感することに重点を置いて接していきましょう。
子どもを焦らせない
お子さんが不登校になった場合、不安に感じるご家庭は多いです。しかし、無理に登校を促したり、強引に悩みを聞き出そうとしたりするのは逆効果になることもあります。
子どもが自発的に行動することを待つ姿勢を崩さないようにしましょう。不登校中は本人にとって休息が必要な時期であることを理解し、今置かれている現実をお子さんとじっくり向き合っていくことを心がけましょう。
学習を効率的に進めてみよう!
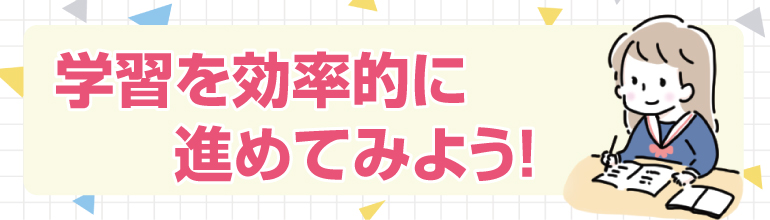
勉強する内容や範囲を決める
勉強に関しても焦らず進めることが重要となります。
教科書の内容をすべてカバーしよう!とあれもこれもと手を広げすぎると、本人の負担が大きくなってしまい、なかなかうまくいきません。
まずは学習内容や範囲を絞ってスモールステップで取り組むよう提案してみましょう。範囲を限定することで勉強に対するハードルを下げ、子どもが「勉強してみようかな」と思える状況を作ることが大切です。
得意科目に集中して勉強する習慣をつける
まずは勉強の習慣を身につけることが大切です。子どもの得意科目や好きな科目など、手を付けやすいところから始めると勉強の習慣がつけやすいです。
必ずしも長時間の勉強がよいわけではありません。15分程度の短時間の勉強を集中して繰り返しおこなうことで、学習内容の定着度が上がります。
こまめな休憩を挟むことで集中力が回復しやすくなり、集中力の持続時間が伸び学習効果が上がります。
苦手科目に取り組むのは学習のモチベーションが上がってから
本人に勉強する習慣が身につき、学習に対するモチベーションが高くなってきたら、苦手科目に取り組みましょう。最初から苦手科目に取り組むと、わからない、意欲が出ないなどのつまずきが出てしまい、学習に対するモチベーションが下がってしまいかねません。
得意科目や好きな科目で分かった!できた!楽しい!などの成功体験を重ね、学習に対するモチベーションを上げてから取り組むことで、苦手科目にもスムーズに着手しやすくなります。
不登校中、学校に通わなくても実践できる勉強方法
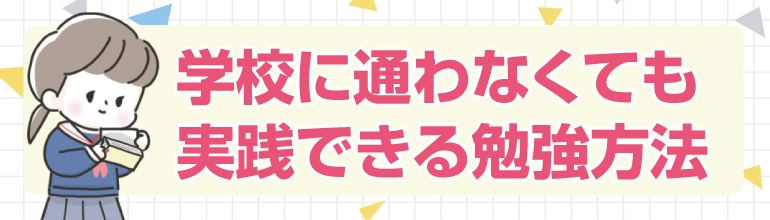
今度は具体的な勉強方法を考えましょう。それぞれの方法と特徴を詳しく解説していきます。
1.問題集などを購入して自主学習をする
学校の教科書や副教材、市販の参考書や問題集などを使用して勉強する方法です。
自主学習は、集団生活や対人関係に悩むことなく、また提出の期限にも追われずに、自分のペースで勉強を進められます。また、自分に合った問題集や参考書を自由に選べるのもメリットです。
ただし、制約の無い中での学習となるので、「勉強のモチベーションを保てない」、「わからないところがあってもそのままにしてしまう」などのデメリットがあります。
2.通信教育を利用する
通信教育では、指定の教材が与えられ、課題に取り組み、添削指導を中心とした勉強方法です。
最近では、自分のタイミングに合わせて学習できるように、動画授業を利用できる通信教育サービスも登場しています。
添削指導の中でやり取りがある通信教育は、勉強中の疑問を解決しやすい利点があります。ですが、教材との相性が悪い場合があったり、自主学習と同じく、自ら学習に向かうモチベーションが大切となるため本人の取り組み次第では、結果が得られにくい場合があります。
3.オンライン学習塾で学ぶ
オンラインでの講義や動画講習と、指定の教材を中心に学習する方法です。
外出が苦手、人と直接関われないなどの傾向があるお子さんにはおすすめの学習方法です。
メールやLINE、塾の掲示板でいつでも指導員に質問・相談できる塾もあり、通信教育以上に疑問を解消しやすく、学習の理解が進みやすいのも特徴です。
4.家庭教師
家庭教師にマンツーマンで指導してもらう勉強方法には、自宅などで、対面で教えてもらう形式のほか、オンラインで学習する形式があります。
日時指定の約束がある分、モチベーションを保ちやすいのが家庭教師のメリットです。講師と直接の交流があるため、学習内容や方法も融通が利きやすいのが特徴です。中には、自宅以外のカフェなどで学習対応をしてくれるサービスがある塾もあります。個々の関係性が近いため、相談相手にもなってもらえるかもしれません。
ただし、他の学習方法と比べて費用が掛かるため、経済的に余裕があるかが課題になってきます。
5.個別指導塾
集中しやすい小さなブースで授業を受ける個別指導塾には、マンツーマンで指導してもらうケースと、2~3人などの少人数で指導してもらうケースがあります。
個別指導塾の中には、不登校の生徒へ配慮してくれるところも多くあり、自宅とは異なる環境に身を置くことで、気分を変えられる効果も期待できます。また、個別指導の場合は講師との距離が近く、わからない箇所の質問がしやすい、自習室がある場合は好きな時間に塾を利用できるなどの利点があります。
講習の時間に合わせて自宅と塾を行き来すると、生活リズムができ、体力がつくなどのメリットもあります。
ただし、学校近隣の塾では、同級生と顔を合わせる可能性もあるため、本人の気持ち次第では、立地や通塾時間などに配慮が必要です。
6.集団学習塾
10~40人程度、あるいはそれ以上の集団クラスの塾で授業を受ける方法です。
大人数での学習となるため、学習に遅れがない、学習に対して意欲的など、不登校の子にとっては少しハードルが高い学習方法です。
受講生を一律に教えるという集団学習塾の仕組み上、個別に細かく対応してもらうのはどうしても困難です。不登校であることに十分配慮してもらえない可能性もあるので、復学に向けた最終ステップとして利用するのがおすすめです。
7.適応指導教室
不登校の生徒を中心にサポートするため、都道府県や市町村が設置している施設です。
主な役割として、
| ・学習指導に関しては、在籍校とも連絡をとり、個別の状況に応じて実施される ・指導内容は、個別指導や集団指導、体験活動など ・心理スタッフによるカウンセリングなどの心理的ケア ・家庭訪問による相談・適応指導や、通室困難な子どもについては、学校や他機関との連携した支援の実施 ・保護者への不登校の態様に応じた助言・援助 |
などがあり、学校復帰を見据えて、子どもの実態や取り組み状況について学校との連携がおこなわれます。また適応指導教室への出席は、在籍校の出席扱いとなります。
通所の際に掛かる交通費や昼食代以外は無料であるのも特徴です。同じ悩みを抱える同年代の友達ができる可能性もりますが、適応指導教室は学校復帰を目的として運営されているため、学校そのものに抵抗があるお子さんにとっては、負担が大きくなる恐れもあります。
8.フリースクール
フリースクールは、不登校の子どもを受け入れることを主な目的とする団体・施設を指し「不登校の子どもたちの居場所」という役割を果たしています。
運営主体は個人や民間の企業、NPO法人によって担われており、様々な規模や形態のフリースクールが存在します。2016年に制定された「教育機会確保法」により、義務教育課程の子どもであれば、もともと通っていた小中学校に籍をおいたままフリースクールに通うことができます。
子どもの自由や個性を重んじながら、子どもが学び育つ機能をもち、不登校の子どもたちにとって社会との接点をもつ場所となっています。ただし、費用に関しては平均3万3000円〜と、フリースクールにより大小様々ですので、その点に関しては注意して探す必要があります。
ネット高校や新しい育英団体への選択肢
将来的に高校卒業資格は取りたいけれど、学校に行けない。という不登校の場合、ネット高校を選ぶ方法もあります。
ネットの高校は、インターネットと通信制高校の制度を活用した新しい高校です。
ICTツールを活用し、効率良く高校卒業資格取得のための学習が効率良くできることで、自らが学びたいことに多くの時間を充てられます。他にも、未来を創る人材を支援することを目的とした孫正義育英財団などもあります。
不登校のサインが見られた場合に、親御さんはどのような対応をするのが良いか、サインによって対応策をご紹介します。
心身の不調を訴えたら、まずは医療機関へ
心身の不調はストレス反応の可能性もありますが、ほかの病気が原因である可能性もゼロではありません。まずは医療機関で診てもらい、原因を特定しましょう。
疾患は無いと診断されても、無理に登校を促したりするのはやめましょう。ストレスが原因であることを踏まえて、次にご紹介する対処を実行してみてください。
お子さんをよく観察して、お子さんの心に寄り添う
「なぜ」、「どうして」この2つのワードは親御さんが持ち出してしまいやすい言葉です。
いくら問われても、お子さんは自分から話してくれないでしょう。焦らず、お子さんの普段の様子をよく観察し、ちょっとした言葉にも注意して耳を傾けてみましょう。
具体的には
| ・無理して登校しようとしてはいないか ・学校生活や日常生活でがんばりすぎていないか ・つらいこと、嫌だと感じていることを我慢していないか |
などの点に注意してみてください。
不登校になりそうな原因やきっかけが少しでもわかれば、さらに次の対処も見えやすくなります。
生活リズムに干渉しすぎたり、登校を無理強いするなど、過度な干渉や無理強いは逆効果です。ますますプレッシャーやストレスを感じて、学校に行きづらくなってしまいます。叱ったり、無理に矯正しようとするのではなく「少しずつでも生活リズムが改善されればいいかな」くらいの気持ちで見守るのがよいでしょう。
また、本人が「学校を休みたい」といってきたら、休ませてあげましょう。夏休み明けの登校に対して、まだ心の準備ができておらず、もう少しだけ時間がほしい可能性があります。1~2日休ませると、学校に行けるようになることもあります。
それでは最後に夏休み明けの登校へ向けてできることをまとめてみましょう。
不登校中の学習まとめ
不登校中の勉強は、学校復帰のために必要ではありますが、まずは焦らず、お子さまに合った勉強方法を見つけることが大切です。中には、学校に行かなくてもできる勉強方法もたくさんあります。
お子さん、そしてご家庭の未来を見据えて、様々な選択肢を持って前向きに取り組んでみてくださいね。
無料相談からはじめてみませんか?
スクールIE吉成校の不登校サポートコースでは、不登校中の学習に関するご相談が無料です。少しでも不安があるならスクールIE吉成校、不登校サポートコースへ皆様の声をお聞かせください。





コメント